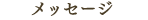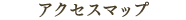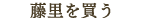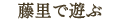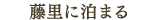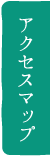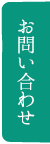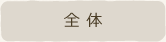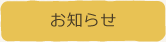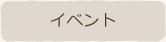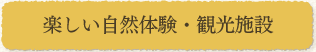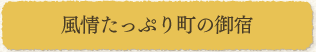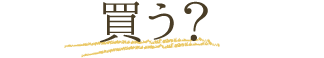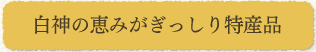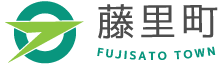The mountainous wilderness of Shirakami Sanchi stretches across 130,000 hectares of Akita and Aomori Prefectures. Of this, 16,971 hectares comprise the largest remaining primeval beech forest in East Asia, one largely untouched by human activity for over 8,000 years. This area was registered as the Shirakami Sanchi World Natural Heritage Site in 1993, and was among the first in Japan to be given the UNESCO designation (along with forests on the island of Yakushima, in Kagoshima Prefecture).
The World Natural Heritage Site is divided into two zones: a protected core zone where access is restricted, and a buffer zone around that core, where visitors can observe much of the same flora, fauna, and terrain that are found in the core zone. Approximately a quarter of the World Natural Heritage Site is located in Akita Prefecture, where access to the site is more tightly controlled than on the Aomori side.
At the heart of the virgin forest’s diverse ecosystem is the buna, or Japanese beech. This keystone species can grow taller than 30 meters and live for centuries. In regions with heavy snowfall, like the northern prefectures bordering the Sea of Japan, beeches have a natural advantage over other species. Young beech trees are extremely flexible, and they bend under the weight of heavy snow that would snap or uproot other trees. As a result, beeches make up a large percentage of the forest. They bear fruit and nuts eaten by animals, and their broad leaves keep the forest cool in summer. After the leaves fall, they contribute to the rich humus of the forest floor. This decaying carpet sprouts undergrowth that, together with the beeches’ roots, regulates water levels and helps prevent droughts, floods, and landslides.
Although old-growth beech forests once covered much of the country, today they are extremely rare. Before their ecological importance was understood, beeches were considered largely useless, their wood unsuited to most crafts or construction. In fact, the character used to write “beech” is a combination of the characters for “tree” and “nothing.” Consequently, many of Japan’s beech trees were cut down in the second half of the twentieth century, and the land was replanted with cedars intended for the lumber harvest. Luckily, the remote location and steep slopes of Shirakami Sanchi protected the area from significant exploitation, preserving it for people today.
In addition to beeches, approximately 100 other tree species and thousands of plant and animal species live in Shirakami Sanchi’s forests. There are 35 mammal species recorded, including the Asian black bear, the Japanese macaque, and the Japanese serow (kamoshika), a bovine that resembles a shaggy deer. Other local fauna include 9 reptile species, 13 amphibian species, and 90 species of bird—including the rare black woodpecker, the largest of its family in Japan.
The steep mountainsides of Shirakami Sanchi are punctuated with deep valleys, many of them carved by swift-flowing rivers and waterfalls. Some of the area’s highest peaks are Mt. Fujisato-Komagatake (1,158 m), Mt. Futatsumori (1,086 m), and Mt. Kodake (1,042 m).
One of the lowest mountains in the region is Mt. Tomeyama (180 m). Tome means “stop” or “prohibit,” and logging was forbidden on Tomeyama’s slopes more than 300 years ago in recognition of the role of the beech forest in preserving local water levels for agriculture. This connection was again brought home in modern times when beeches near the Subari Dam were felled, resulting in a significant drop in Subari Lake. This event proved a catalyst for protecting Shirakami’s forests and gaining recognition as a World Natural Heritage Site.
----------------------------------------------
日本語訳
秋田県と青森県にまたがる白神山地の原生地域は、130,000ヘクタールに広がっている。このうち、16,971ヘクタールが東アジアに残る最大のブナの原生林であり、8,000年以上にわたって人間の活動の影響をほとんど受けていない。この地域は1993年、日本で初めて世界自然遺産白神山地としてユネスコに登録された(鹿児島県の屋久島の森とともに)。
世界自然遺産は、立ち入りが厳しく制限され保護されている白神山地核心地域と、その周りの緩衝地域の2つのゾーンに分かれている。緩衝地域では、核心地域と同じ動植物や地形を観察することができる。世界自然遺産地域の約4分の1は秋田県にあり、青森県側よりも立入りが厳しく管理されている。
原生林の多様な生態系の中心にあるのは、ブナである。キーストーン種であるブナは30メートル以上に成長し、何世紀にもわたって生き続けることができる。日本海に面する県北部のような豪雪地帯では、ブナは他の樹種に比べて自然の優位性を持っている。ブナの若木は非常にしなやかで、他の木が折れたり根こそぎになったりするような大雪の重みにも耐えられる。その結果、森林の大部分をブナが占めている。ブナは動物が食べる果実および種実をつけ、ブナの大きな葉は森を涼しく保つ。落ちた葉は林床の養分豊富な腐植土になる。この腐朽した絨毯は、林床から下草を生やし、ブナの根とともに山の貯水量を調節し、干ばつ、洪水、地滑りを防ぐのに役立つ。
かつて、ブナの原生林は国の大部分を覆っていたが、今日では非常にまれである。ブナの生態学的重要性が理解される以前は、ブナはほとんど役に立たない木であると考えられていた。工芸品の材料や建築木材として適していなかったからである。実際、「ブナ」を書くときに使用される文字は、「木」と「何もない」を意味する文字の組み合わせである。その結果、日本のブナの木の多くは20世紀の後半に伐採され、収穫後に木材として使われるスギに植え替えられた。幸いにも、白神山地は人里離れた場所にあり、山の斜面も急であることから、大規模な伐採から逃れることができ、現在まで保護されることとなった。
白神山地の森には、ブナのほか、約100種の樹木や数千種の動植物が生息している。ツキノワグマ、ニホンザル、ニホンカモシカ(カモシカ)を含む35種の哺乳類がいる。ニホンカモシカは鹿に似た毛むくじゃらのウシ科の動物である。その他の動物としては、爬虫類9種、両生類13種、鳥類90種が生息しており、その中には、日本最大のキツツキの仲間であるクマゲラがいる。
白神山地の山腹の急斜面からなる深い谷があり、その多くは流れの速い川や滝によって形成されている。この地域で最も高い山の中には、藤里駒ヶ岳(標高1,158m)、二ツ森(標高1,086m)、小岳(標高1,042m)がある。
この地域で最も低い山の1つは、留山(標高180m)である。留山の「トメ」は「止める」または「禁止する」を意味し、300年以上前に留山の斜面での伐採が禁止された。これは、ブナ林が地域の農業水を蓄える働きがあることの重要性を認識していたためと思われる。ブナと水との関連性は、近代になって素波里ダム近くのブナが伐採されたときに、素波里湖に大量の水が流れ込んだことで再認識された。この事実は、白神の森を保護し、世界自然遺産としての承認を得るためのきっかけとなった。