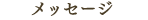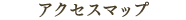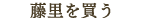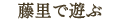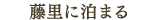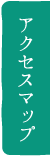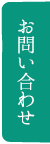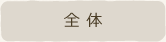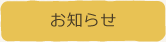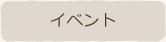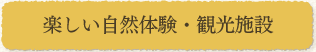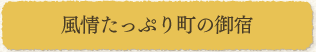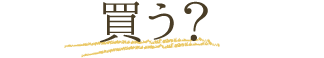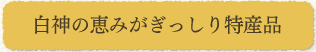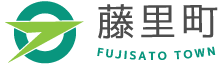Sake Breweries(白神山地の日本酒)
.jpg/DSC00908%20(2)__480x320.jpg)
Sake, or nihonshu, is a fermented alcoholic drink made from rice, fungus (kōji), and water. It has been drunk in Japan in various forms since before recorded history. The mountains of Shirakami Sanchi yield pure spring water with a low mineral content, and the fields produce rice known nationwide for its delicate taste and aroma. Together, they are the key to the region’s excellent varieties of local sake.
By the sixteenth century, sake brewers had established most of the techniques that continue to be used by their successors today: polishing the rice grains, a heated pasteurization process, and the use of large wooden tubs for storage. In the nineteenth century, brewers began to add a type of fungus called kōji to steamed rice to cause fermentation. This is one of several aspects that creates variety in the finished taste. Another important factor is polishing the rice—specifically, how much of the rice grain is ground away. As more of the protein-filled outer hull is removed, the remaining starch-filled center makes up a greater percentage of the fermentation mixture, altering the final flavor. For the premium sake known as daiginjō, at least 50 percent of the rice grain must be polished away, while as much as 70 percent of each grain is removed for the most expensive varieties.
There are two sake breweries on the Akita side of Shirakami Sanchi: Yamamoto Brewery and Kikusui Brewery.
Yamamoto Brewery
Yamamoto Brewery in Happō was established in 1901 in what was then the small fishing village of Hachimori. To pipe fresh spring water to the brewery’s seaside location, community members laid a private waterline over 3 kilometers long. Although it was originally run under the direction of a master brewer (tōji), in recent years the brewery has adopted a more communal, employee-driven system.
Yamamoto Brewery produces junmai sakes (made without the addition of sugar or distilled alcohol) in several grades. Because junmai relies so heavily on rice for its flavor, rice quality is of the highest importance. Yamamoto Brewery cultivates its own rice to ensure standards are met. Roughly half is grown organically, with no pesticides or chemical fertilizers.
Kikusui Brewery
Kikusui Brewery in the city of Noshiro began operation in 1875. The brewery stores its sake underground in a 100-meter-long former railway tunnel built in 1900; this keeps the sake at an ideal 12°C year-round. Kikusui produces a wide range of sakes, from inexpensive varieties to daiginjō priced at ¥100,000 per bottle. The brewery values its regional identity and its strong connection to the town of Noshiro.
Changing with the Times
Despite sake’s lengthy history, nationwide production has shrunk to a third of its early 1970s peak as consumers—particularly young people—have shifted to drinking other beverages. In response, five Akita breweries with lineages dating back 100 to 330 years formed a group to collaboratively revitalize their businesses. Calling themselves the “Next 5,” these comparatively young owners were facing similar problems, such as conflicts with their breweries’ older master brewers, who were often resistant to new ideas. Now the Next 5 owners are working together to create new beverage varieties (such as sparkling sake) and marketing strategies that appeal to younger drinkers, as well as expanding into overseas markets. One of the Next 5 members is Yamamoto Tomofumi, owner of Yamamoto Brewery, which now exports to 12 countries.
-----------------------------------------------
日本語訳
日本酒は、米、酵母、水から作られた醸造酒である。日本では有史以前から様々な形で飲まれてきた。白神山地では、山からミネラル分が少ないきれいな湧き水が流れ、平地の稲田ではその繊細な味わいと香りで全国的に知られる米がつくられている。これらが一緒に組み合わさって、この地域の優れた地酒ができる。
今日受け継がれている日本酒の製造技術のほとんどは、後継者たちにより、16世紀までに確立されたものである。それらは、精米、加熱殺菌工程、木樽での貯蔵などである。19世紀になると、蔵元たちは、蒸し米に麹と呼ばれる酵母を加えて発酵するようになった。これは、日本酒の味わいに多様性を与える要素の一つである。もう1つの重要なファクターは、精米である。具体的には、米粒のどれだけの割合を削り取るか、ということである。タンパク質の外皮が取り除かれると、残りのデンプン質の中心部が発酵混合物のより大きな割合を占め、最終的な風味に変化を与える。大吟醸として知られる高級酒の場合、米粒の少なくとも50%を除去する必要があるが、最も高価な品種の場合、ひとつひとつの米粒を70%も取り除かなければならない。
白神山地の秋田側には、山本酒造店と喜久水酒造の2つ酒蔵がある。
山本酒造店
八峰町の山本酒造店は、1901年に当時小さな漁村であった八森村に創業した。新鮮な湧き水を海辺にあった蔵までパイプで送るために、村民は長さ3kmを超える自家水道管を敷設した。当初杜氏による管理体制だったが、近年では従業員が主体的に取り組める体制を採用するようになった。
山本酒造店では、グレードの異なる純米酒(糖分や醸造アルコールを添加せずに製造)のみを生産している。純米はその風味を米のみに頼っているため、米の品質が最も重要である。その卓越性を堅持するために、山本酒造店は自ら酒米を栽培している。約半分は有機栽培で、無農薬および無化学肥料で栽培されている。
喜久水酒造
能代市の喜久水酒造は、1875年に創業した。喜久水酒造は、1900年に建設された長さ100メートルの鉄道用地下トンネルの跡地を日本酒の貯蔵庫に使用している。これにより、一年を通じて理想的な室温である12度に保たれている。喜久水酒造では、安価な銘柄から1本10万円の大吟醸まで、幅広い価格帯の日本酒を生産している。また、地域のアイデンティティと能代の町との強いつながりを大切にしている。
時代とともに変化する
日本酒の長い歴史にも関わらず、全国的な生産量は1970年代初頭のピークの3分の1にまで縮小している。それは、消費者、特に若者が他の飲料を飲むようになったことが影響している。そこで、100~330年の歴史を持つ由緒ある5つの酒造会社が、事業を活性させるためグループを結成。自らをNEXT5と呼ぶこれらの比較的若い経営者らは、新しいアイデアに抵抗することが多い年上の杜氏との対立など、同様の問題に直面していた。彼らは協力して、新しい飲料(スパークリング酒など)の醸造、若年層の消費者に訴えるマーケティング戦略の立ち上げ、海外市場への進出に取り組んでいる。山本酒造店の現在の蔵元である山本友文はNEXT5の一人であり、山本酒造店は現在、12カ国に輸出している。