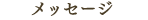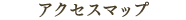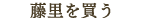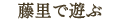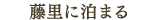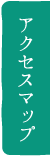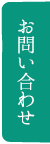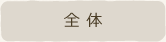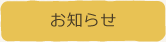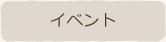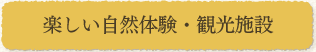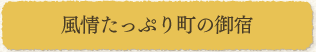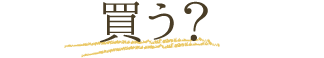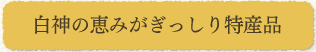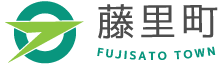【後編】
営業終了いたしました。

居間に飾られていた、米粒を貼り付けて作った色紙。好きなトミさんは「和」という字が好きなので、農家民宿の名前も「和らぎ荘」に。
藤琴川にかかる藤琴橋の手前にある、粕毛地区。農家民宿6軒にうちの1軒が「和らぎ荘」です。桐越智嗣さん、トミさん夫妻がここを営み、藤里町のよいところをおもてなしの心で伝えてきました。
民泊での出会いや趣味の畑づくりについて伺った前編に続き、民泊での様子や様々な会の代表をして活動する様子を教えて頂きました。
冠婚葬祭で頼まれるほど料理が上手だった、母の影響を受けて今に。
トミさん:民泊は月に1、2回でしょ。気をつわないから疲れないよ。泊まりに来た人が家に入る時に、田舎だと思ってと言うの。田舎がない人もいるし、寒いけれど寒いのがよくて来るんだから。こえー(秋田弁で疲れた)と言わないから、無理しない程度に動いているんだろうなあ。できないことはやらないし、刺し子も飽きてきたし(笑)。今は、牛乳パックのイスづくりをしていて、これから内側にラップの芯に入れて丈夫にするところ。工業用ミシンでバッとカバーを作ったり、レースやアップリケ、取っ手もつけるよ。
団体が民泊に来る場合、公民館で交流会を開くことが多いよ。前日から買い物して、当日も9時ごろまで飲んで、帰ってきて12時ごろに寝るような感じ。「ブナの森マラソン」で泊まった時は、6時前に出て行くから、5時には起きて朝食と昼の弁当も用意してとなかなか大変。寝る時間が少なくなってしまうのは課題だけれど、秋田に興味を持ってくれたり、みんな喜んでくれるからねえ。事務局にこれまで不満とかないの?と聞いてみたけれど、ないって。
特に女の人は興味があるみたいで、今まで見たことのないものを食べて、こういうふうにして作るんだとメモしていくことも。旬のものを使ってタケノコの天ぷらを揚げてみたり。そういえば、岩手の遠野で干し柿の天ぷらが出たことも。
昔、惣菜、仕出し屋がない時代に、冠婚葬祭があると母親がよく料理を頼まれていて。ドライブインに入って食事をした時に、これどうやって作ったのかなと興味を持って、あとで必ず挑戦する人だった。漬けものが上手で、自分で作った野菜で漬けて、藤里のお店にもおろしていたこともありましたなぁ。

家の中にあった古い時計。現在は止まっているが、古いものを眺めるのも楽しい。
人が増えることもあるから料理は多めに作るよう、母に教えられました。
トミさん:ここで集まりとか何かあれば、うちに20人位来るよ。二人とも昭和18年生まれで75歳。気持ちだけ元気(笑)。中学校が同じで、何か縁があって一緒に。もう大分捨ててしまったけれど、30人も泊まれるくらい布団があったから。藤琴小学校とかスキー部とかの同級会があって、二次会、三次会となれば、全員うちに集まってきた。来た時に履かせればと思ってパンツもサイズ違いで用意しているのよ(笑)。
お父さんが同級生だから集まりやすいんじゃないかな。最近は年をとって、あまりなくなってきたけれど。母には、人が増えることもあるから多めに作っておくものだよと教えられた。なんでこんなに作るの?と言われることもあるけれど、習慣になっているんだな。カレーを作って、学生がお代わりできないのはかわいそうだから、多めに作るようにしています。
民泊をやっている仲間で集まった時に、経験したことを話すようにしてる。一緒に料理をするとなると十人十色みんな違うから、その担当する人の味でやったらと私は言うのよ。ご飯の炊き方も人それぞれ違うし、人数が違うと勝手が変わっていつもとは違うこともある。そんな時はみんなで話して、合わせていければいい。
ただ、秋田の恥になるから、変なきりたんぽは出せない、やり方は統一しないとという気持ちはあります。親のやり方もみてきているし。社協(社会福祉協議会)の厨房で働いた経験もあるから、こうだよーと教えています。おかしいと思ったら、素直に話せばいい。最初は遠慮して難しいなと思ったこともあったけれど、今は楽しんでうまくやっていますよ。

10年近く飼っているという和金。ある日突然体が白くなりったそう。優雅に泳いでいる様を見るだけでも癒やされる。
受け入れ前は心配もあったけれど、今は楽しみながら。
智嗣さん:民泊をやるのは、実は乗り気でなかったけれど、お母さんがいろんな人との出会いがあるから、始めることにしたんだ。
トミさん:私は婦人会の会長も「和みの会」(趣味のグループ)もやっているし、前に民泊の話があった時には興味がなかったけれど、岩手の遠野に体験に行かないかと誘われて粕毛の仲間と岩手の研修に行ったのが2年以上前でしょう。泊まったところの奥さんと意気投合して楽しかったし、お父さんと二人いるからやってみるか、という気持ちでスタートしたんだよね。
体験しないとそうはならなかったと思う。他人を入れることには警戒心もあるし、息子にも心配されたよ。でも、持って行かれても心配されるものもないから心配するなって言った(笑)。自分が作ったものでもおいしいって食べてくれるし、みんな喜んでくれる。これが民泊のいいところだな。でも、お腹が痛くなったとか、それだけは心配だけれど。そこは気を引き締めて、マスク被って気をつけてやるよ。
智嗣さん:子どものアレルギーは気をつけないとな。
トミさん:ソバ、卵がダメな子が1人いて、うちに来てから分かったの。それからは事務所でも事前に確認するようにしているし、自分も聞いています。たくさん儲けられるものではないけれど、ひとつのビジネスだから、事務局には全体に伝えたいことは文章で残してくださいとお願いするようにしているよ。
あと泊まる人がうちのトイレに貼ってある藤里町のカレンダーを見て、関心持つことも。お父さんは町に詳しいから、町のアピールをしてくれる。2人でバッテリー組んでもてなしできていていいのかな。
今は自分たちも楽しんでいるし、いろんな出会いがあっていいもんだよ。今民泊をやっているのは6軒。ここまで頑張ってきたから、あとに続く人が出てくればいいな。せめて60歳くらいの人にやってもらえればうれしいし、バイキングでもいいから手伝いに来てくれればいいなと思う。
衛生に気を遣ってご飯の支度をしている。
和みの会を主宰。仲間たちと笑って、楽しい時間を過ごしています。
和みの会をやっていて、そこにあるものは、全部作り方を教えた時にできたものなの。危ないから針は使わないようにして、2時間でできそうな、お金かからないものを選んでやっているの。100円ショップで材料を買ってきて何かを作ることもあるし、社協からゲーム借りてきて遊ぶことも。
そういうことをやっていれば、寝ていられないよ(笑)。みんな仲がよくて、集まってくるから楽しい。社協を辞めた後に、月一回でもいいから人を集めて何かやりたいと思ったの。反対もされたけれど、パソコンでチラシ作って、やりませんかって呼びかけようとも思ったのですが、口コミで初めてみたの。
20年以上の付き合いがある、5人会というのをやっていてね。ごはんを食べに行ったりしている仲なんだけれど、仲間に相談したら、いいことだからやれって言われたの。私が会長で責任を取るし、やってみないと分からないからって始めてみた。
会費を200円を集めて、消費税上がってからは250円集めて、昼ご飯を食べるようにしたの。みんなで流しに立って用意して、保健師さんに血圧測ってもらったり、いろんな人を呼んできて認知症の話やオレオレ詐欺の話をしてもらったり。保健師さんに自分の体調や家族のことを相談する人もいるよ。17人でスタートしたんだけれど、今は30人の会になったよ。ものづくりして、分担してご飯作って。もう、6年目に突入しました。
智嗣さん:女性たちは調理できる。お金が少なくても楽しめるから、いいな。
トミさん:自分の家で採れたものは提供してもらって、それでたんぽ(きりたんぽ)作りとかすることも。でも、米は会費で買うし、買ってまで持ってこないでとお願いしています。既製品も、材料を買ってケーキやプリンも作るのもダメ。デザートは会費で買うから。
集まって笑って笑って、一日笑っていく。60代から、上は84歳まで。出入り自由、顔だけ見せていく人もいるし、ご飯を食べて帰る人も。”和”という字が好きで、だからここの民泊の名前も「和らぎ荘」にしたの。”和”は、一番いい字だと思う。いろんな読み方もできるしね。和に成れって、息子にも和成と付けてるくらい好きなの。昭和、平成、令和って年号が変わっても、和と成が入ってて、また令和ってきたからびっくりだよね。息子の誕生日がなんと5月1日だったもんだから、元号スタートと一緒で、まして縁を感じてるの。
あとは、27歳の時から保険の還付金を貯めて旅行へも行っていて、今度の50回の節目で解散しようかなと思っているところ。この会に入っていたおばあさんたちが亡くなると、今度はお嫁さんたちが入ってきて、という感じでもう50回も続いているの。次の旅行の時に発表するつもり。27歳から始めて50回続けてって、歳分かるでしょう(笑)。これにもハマってしまったんだよね。

トミさんが立ち上げ、毎月開催している「和みの会」。低予算でも手作りできるものをトミさんが教えている。その時に作った作品の数々。
人を迎え入れる民泊。気はつかわなくても、簡単な気持ちでは受け入れない。
トミさん:岩手に視察に行って、誰かが旗揚げしないとと思って始めた民泊ももう3年目。振り返らない、前進あるのみだよね。どこまで行けるか分からないけれど、助け合ってできるところまではやるつもり。人相手の仕事だから、簡単な気持ちではできないといつも思っているよ。
社協に入る前に鷹巣で働いている時はものを扱う仕事だったけれど、社協は人を扱う仕事でしょう。入って1か月くらいは、怖かったよ。現場向きだと言われて3年で現場の仕事になって、ハイエースに4台も車椅子を乗せるの。お風呂連れていくのも大変。この前、車椅子を押している人をどこかで見て、坂道はバックで下りないといけないよーと思わず声が出てしまったほど。
人を扱う仕事だから、しっかりミーティングするようになったりして改革が進んだの。こんな経験をしたから、民泊をやるにも責任を感じながらやっている。泊まりに来た人が咳をしていたら気になるしね。迎え入れる時は、いらっしゃいじゃなくて、お帰りなさい、出て行く時は行ってらっしゃいと言うし、自由にしてくださいとも。こちらも楽だからだからね。じゃないとやっていけないよ。自分を持たせるたまには自分流でね。
シーツだってタオルだって洗濯もしないといけなし、電気、水道、ガスも使用料が上がる。大きく儲けられるわけじゃないけれど、楽しくやっているからいいかな、出会いがいいなと思う。つながってたまに電話で話せる人もできて、いいなと思うよ。

居間にある装飾品を説明してくれた智嗣さん。町のことに詳しく、宿泊する人には町の魅力を伝えている。
*旅する藤里 まとめページへ
https://www.town.fujisato.akita.jp/kanko/notices/2496
ライター : 久保田真理(くぼた・まり)
ライフスタイル誌の編集者、オーストラリアでの写真留学を経て、フリーランスとして独立。国内外の取材を通じて、多様な生活や文化の魅力を発信する。秋田市生まれ、茨城・千葉育ち。趣味は、日本酒、トレイルランニング、ソウルミュージックの世界に浸ること。
知られざる藤里の旅は、“大切なものは何か”気付かせてくれるはずです。
このコラムは聞き書きの手法で藤里町ツーリズム協議会が制作しお届けしています。
藤里町ツーリズム協議会 電話0185-79-2115
*白神山地ふじさとのストーリーが届くフェイスブックはこちらです*
フォローすると定期的にストーリーが届きます
https://www.facebook.com/fujisato.syoukoukankou/