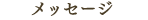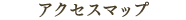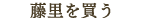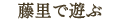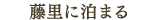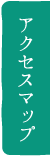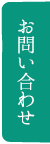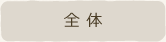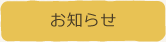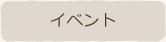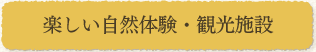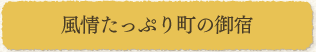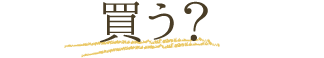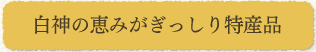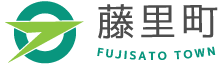【前編】
営業終了いたしました。

桐越智嗣さん、トミさん。それぞれ好きなことを楽しみながら、町のため、町民のためにいろいろな活動を行っている。
藤琴川にかかる藤琴橋の手前にある、粕毛地区。農家民宿6軒にうちの1軒が「和らぎ荘」です。桐越智嗣さん、トミさん夫妻がここを営み、藤里町のよいところをおもてなしの心で伝えてきました。
民泊を通じての出会いや、趣味の畑づくり、養鶏などについて、話を伺いました。
私が手芸や料理を教えたり、お父さんは一緒にお酒を飲んだり。
智嗣さん:今から2年ほど前、ここの粕毛地区の仲間と岩手の遠野へ研修に行って、民泊を始めました。知らない人を自宅に泊めることに、最初は心配もあったけれど今までトラブルもなく、民泊を楽しんでいます。アークと言う秋田大学中心の地域おこしをする学生サークルが、日本語の分からない外国人を連れて来たことがあって、こちらも英語が話せたらいいなあと思ったけれど、70歳も超えてきたからね。通訳がついて話をして不自由はないし、来る人たちが日本語勉強してねという気持ちで気負わずにやっています。
トミさん:その時、受け入れる側も英語を少し話せるようになって欲しいとリクエストがあったけれど、遠野で民泊体験した時に突っ込んで聞いてみたことがあったのね。そうしたら、秋田の言葉でいいと言われて。民泊をする人はそれが良くて来ているんだし、ジェスチャーでいい。多少言葉の問題があっても、女の子なら手芸、料理を教えればいいし、飲める人はお父さんと飲むし。
始める前は、一期一会かなと思っていたけれど、時折電話をくれる人もできました。昨年10月にこの粕毛地区の人たちと神奈川県藤沢市に行って特産品を売っていた時、ここに泊まったことのある夫婦が遠くから手を振ってくれてね。こんなふうに気が合って親戚以上の付き合いになった人もいますよ。いつか、温泉が好きでない人が来た時には、他の人たちが温泉に行っている間に、野菜を収穫したり、飼っているニワトリの卵を取ったり、あとはだまっこもち(鍋に入れる白米を潰して丸めた郷土料理)を作ったり。
タイ人の夫婦が来た時は、おじいさん、おばあさんの家に来たみたいと言って、朝からなんでも手伝ってくれたよ。キッチンから料理を運ぶのもね。気をつかわないのがいいみたい。何度も来る学生さんが、「おばさん、成人になったよ」と言うのでちょっと飲ませたらデンとひっくり返ったりね。おもてなしの心で秋田のことを教えてあげられたらいいなと思ってやっています。ここでしか食べられないものを出したりとかね。

トミさんが最近夢中になっているという、牛乳パックを利用したイスづくり。ミシンでカバーを縫い、アップリケなどの装飾はお手のもの。
学生さんたちも宿泊。孫と一緒にいるような感覚で接しています。
智嗣さん:民泊は旅館とは違うから、堅苦しく考える必要がないと思う。民泊を始めるのにどこも直したりしないで、そのままの家に泊ってもらっています。ここの家は元々は茅葺きで、昔は土間もあったよ。食べ物、言葉、田舎のやり方を教えてあがることが民泊のいいところ。ステーキ、洋食は出せないけれど、そういうおもてなしを求める人はホテルに行けばいいしね。比較的年配の人たちが多いけれど、サークルの学生さんたちもよく来るよ。
トミさん:なかには涙を流して悩み事を話す学生もいたね。じいさん、ばあさんの家のつもりで気をつかわなくていいよとこちらも言うし、私たちにも男の子の孫がいるから慣れているから話しやすかったのかな。話したら気が晴れたみたいで、いっぱいご飯を食べさせて。いつでもおいで、って言って、その後も別の用事で町に来た時に、時間ができたと言ってうちにも寄ってくれるよ。
あとは、一緒に来た友だちがトイレから出て来ないというのでコインでドアを開けたら、中で寝てたなんてことも(笑)。民泊をやっているといろんなことがあるよ。また来ますと言うけれど、みんな料理も家も違うから他にも行ってみたら、と送り出します。
宿泊した学生たちと食卓を囲むトミさんと智嗣さん。
私は農家の娘に生まれて、何でもやってきた。
トミさん:私は畑とニワトリが趣味なの。お父さんは私が居ない時に餌をやるぐらい。私は農家の娘で、実家には牛、豚、鶏、犬も猫もいて、残飯集めて餌にしたり、納屋の肥やし出しも。製材場からおがくずをもらってストーブに使ったりもね。あと、本家の田んぼの手伝いをしなくてはいけなかったの。
お父さんは私が何かやったら片付けはしてくれるけれど、全然できないの。夏はアユ釣り好きで、弁当作ってやると竿を持って毎日行ってしまう(笑)。去年はニワトリを12、13羽飼っていました。自分で解体もするよ。たんぽ(きりたんぽ。秋田の郷土鍋)だと、放し飼いにした鶏のガラと肉とは、脂が全然違う。そういうのを食べてきているからね。
仲間たちはじゃがいもとか畑のものを持ってくるので、自分のところの卵で返します。お肉をあげることもあって、お父さんには手伝ってもらうけれど、しめるのはできないから。そういうふうに育ってきたから、仕方ないんだ。親にやれって言われれば男も女も関係なかったからね。なんでもしなくてはいけなかったから、やったことがあることはできるんだね。

神棚の前にある鈴。森のえきでも売られている。
あらゆる野菜を育て、子どもや親戚、近所の人に喜ばれています。
トミさん:家の裏と、少し離れた所に畑があって、肉魚はお店で買うけれど、あとはほとんど自家製で食べているの。冷凍できるものは冷凍してとっておいてあるから、冷凍庫2つ満杯になっている。
いろんなものを植えているね。ジャガイモ、ホウレンソウ、春キャベツ、ハクサイ、エンドウ、ナス、トマト、キュウリ、かぼちゃ さつまいも ニンジン チンゲンサイ、ダイコン、パプリカ、ピーマン、ブロッコリー、カリフラワー、ネギ、花菊も。鶏用にニラを植えているし、鶏はサトイモ ズッキーニが大好きだね。
娘、息子、親戚にあげる分も作るから、甥っ子も苗買って来てって言ってるよ。豆とり用も植えるし、サヤを食べる用も何種類も。少しずつ時期をずらして植えて、おもしろいよ。アスパラもかなり植えている。去年は雨が降って不作だったけれどね。
草取りしていて、小さい時に見たことのない草がいっぱいあることに気づくの。恐らく牛糞が原因で、外国製の餌の中に入っている種が消化されずに残って、畑にまかれるんじゃないかな?草取りしていても、草が勝つか私が勝つかという感じで威勢が良い。除草剤を通路にはまいても食べ物にはかけられないから、手で草を抜いている。娘は収獲にだけくるから(笑)。
去年落花生植えたら、たくさんなる、なる、なる。岩手で泊まった家で落花生やっていて、種をもらってきたけれど、最初は雨にやられてならなかったの。それで昨年またチャレンジしたら、黄色い花が落ちてつるが土に入っていって、入ったところ全部に実がつくの。つる同士がぶつかったところは入っていかないから、今度はもう少し間隔をあけてやるつもり。塩ゆでしたら、やめられないおいしさだよ。
落花生もそうだけれど、ニンジンはぶつからないように植えるのがポイント。落花生は5月20日ごろ、田植えの時期に植えればいいって話で。あとは、水はけのいいところに植えるのことかな。ニンジンは育てるのに難しい野菜で、離して植えて間引きして、土をちょこちょこかけるのが大事。そうしたないと葉が傷んで、緑にならないから。
町民祭の時に開かれる産業祭に出品する用にと、まだニンジンが小さい時に何度か間引きして1つを残して、頑張って最後まで大きくなってくれな、って声をかけるの。最優秀賞をとったこともあるし。親も何度も賞をとっていたから、親ゆずりだね。天候によるところも大きいから、雪が少ない年は怖いよね。昨年は11月から降らなかったから、今年の作物に影響があると思う。

桐越家には、古い置物や飾り物がたくさんある。
畑で採れたものをニワトリのエサに、ニワトリの糞は畑の肥料してリサイクル。
トミさん:鶏を飼うのは、勤めを辞めてからだから、10年にもなるかな。4月から11月までで、夏になると卵を産みます。育てた葉ものの半分は鶏用。飼料だけじゃなくて野菜も食べさせるから、脂が違う。漬物の時に出た野菜くずでもなんでも煮て冷凍庫に入れておいて、春になれば飼料と混ぜて出す。手間はかかっているよ。でも、好きだから、夏は4時ごろに起きて小屋に行くよ。
ここの地区の仲間達はブラックベリーを栽培しているけれど、夏の収獲には参加できないの。どうしても餌を8時前に食べさせないといけないし、小さいなら小さいなりの食べさせ方もあるし、産卵時期になるとまた違う。規則正しい時間にやらないと、産卵の産卵率もタイミングも違ってくるから。
あとは水を切らさないように注意している。熱中症にかかって、フカフカと動けなくなったことがあってね。予防注射をしているけれど個体差があって、鶏は暑さに弱いね。熱中症にかかった時は、タンクで水を運んで、2日間だまって水に入って元気になってくれるの。
小屋の掃除をして、肥やしを畑に使ってリサイクルしているよ。食べさせている餌も自家製でよく分かっているから安心で、いい肥料になるんだよね。よくやるなと言われるけれど、親がやっていたのを見てきているからできるんだよね。トサカが赤くなってくると卵を産む時期がきたなと分かって、がんばって産めよ、と声をかけます。飼っている人をよく見ていて、おもしろいものだよ。
卵を産む時期に民泊があると、朝ご飯に卵を出しています。2つ黄身が入ったものを出すと、驚かれるね。肉はあさっさりしていて、脂も柔らかい。2年目になれば肉は硬くなって食べられないの。ダシにするにはいいけれどね。

自宅の裏にある、養鶏の小屋。4月から11月まで、トミさんが大事に鶏の世話をする。手塩にかけて育てた鶏の味は、市販品とはまるで違うとか。
(後編へ続く)
*旅する藤里「和らぎ荘」 後編
https://www.town.fujisato.akita.jp/kanko/notices/1953
*旅する藤里 まとめページへ
https://www.town.fujisato.akita.jp/kanko/notices/2496
ライター : 久保田真理(くぼた・まり)
ライフスタイル誌の編集者、オーストラリアでの写真留学を経て、フリーランスとして独立。国内外の取材を通じて、多様な生活や文化の魅力を発信する。秋田市生まれ、茨城・千葉育ち。趣味は、日本酒、トレイルランニング、ソウルミュージックの世界に浸ること。
知られざる藤里の旅は、“大切なものは何か”気付かせてくれるはずです。
このコラムは聞き書きの手法で藤里町ツーリズム協議会が制作しお届けしています。
藤里町ツーリズム協議会 電話0185-79-2115
*白神山地ふじさとのストーリーが届くフェイスブックはこちらです*
フォローすると定期的にストーリーが届きます
https://www.facebook.com/fujisato.syoukoukankou/