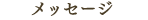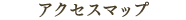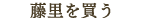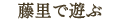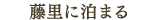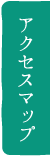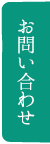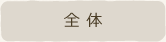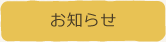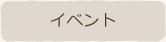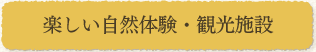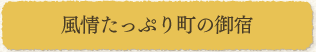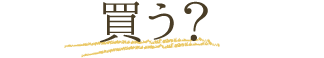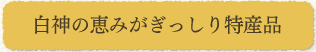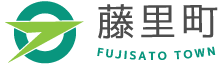【前編】
.jpg/1(2)__600x411.jpg)
工房で愛用の機器を説明する菊地整さん。こだわりのお菓子はここから生み出される。
藤里町の「白神街道ふじさと」(産直)や「白神山地 森のえき」など、町内で作られた商品が並ぶ店には必ず置かれているそば粉のロールケーキやラスクなどのお菓子。手に取ると、「菓子工房 えすぽわーる」と書かれています。
えすぽわーるとはフランス語で“希望”という意味です。清水岱でこの工房を営む菊地整さんに、工房を始めたきっかけや、お菓子づくりへの思いについて伺いました。

工房は清水岱地区にあり、隣には白神の恵体験工房やアルビオン清水岱研究所がある。
郷土愛の強い主人と2人で始めたものづくり
私は秋田県能代市出身ですが、銀行員だった主人が藤里町の出身です。夫は郷土愛が強くて、転勤でいろんな土地で暮らしましたが、いつも藤里と比べていて、藤里町で何かできないかと思っている人でした。
人口が減って土地が荒廃していく町の姿を見て、定年後に町の土地を活用することを考えていたのですが、55歳でひと区切りしたい気持ちになって、その前から具体的に行動を起こそうということになりました。
私は食を手作りすることが好きでずっと実践してきた経験があったので、私たち二人で何ができるだろうかと考えた結果、荒廃した土地でもできるソバを育て、これを原料にして何かできるのではないかとスタートしました。
私は小さい頃から、食べることも、作ることも好きでした。結婚して主婦になり、家族に手作りのものを食べさせてきました。ここで何かしようとなった時、主人には「やればできる大丈夫だ」と言われて、錯覚を起こしましたね(笑)。
.jpg/3(2)__451x600.jpg)
昨年で創業10年を迎えたが、振り返れば10年もあっという間だっという。
食でつながってきた家族
私は子供のおやつや、バースディケーキも手作り。外に食べに行くこと、買うこともいいけれど、手作りできるものは挑戦してみようという気持ちでした。食べることへの興味を持ったのは、母の影響が強い。手土産を手作りするような人でしたから。おやき、すましもち、おはぎなど、米粉とアズキを使ったものが多かったと記憶しています。
自分の子供たちにも、食を手作りすることがつながっていって欲しいなあという思いがありました。外食は特別な時でないと行かなかったから、外食となると余計に楽しみになる感じで育ったように思います。
お菓子の作り方は、本を買ってみたり、講習会に行ったりして覚えました。あと、本や道具をスムーズに用意できたので、理解のあった家族には感謝しています。そして何よりも、家族が食べて喜んでくれる。だからやってこられたのかなと思います。
子供は長男、長女、次男の3人。長男は昨年東京から秋田へ転勤になり、長男家族と秋田市で同居しています。長女も次男も関東に在住していますが、離れていても集まろうとなったらそれぞれの家族が大集合します。あの時食べたあの味懐かしいとか、あれをまた食べてみたいとか、食の話で盛り上がります。
子供の頃食べたカレーで記憶に残っている味が、ホワイトカレー、和風カレー、牛すじカレーだと話題にでました。今はネットで簡単に検索ができる時代でしょう。似てるレシピがあったよと教えてくれたりします。今度は3種類作ってみんなで食べてみようなんて話になったりします。食でこんなにつながっていたとは、予想外のことでした。でも大事なことですね。

こだわりがつまった商品が並ぶ店内。
背中を押され、見切り発車で始めた
ソバにこだわってソバのお菓子を作りたいと、秋田市にある「秋田県総合食品研究センター」に通いました。当時はソバのお菓子がなくて、今までにないお菓子が作れないかという気持ちでした。
ここ藤里町には白神山地があります。そこから採取された天然酵母の「白神こだま酵母」を使ったお菓子はできないか、研究センターに相談に行っていました。
藤里で栽培した最初のソバ粉を持って行き、本来ならば門前払いになっていたところを主人が風穴を開けてくれました。こだま酵母の研究に関わった高橋慶太郎さんに会うことができ、自分たちの思いを伝えました。
ソバ粉にはグルテンがなくてまとまりにくいので、小麦粉を入れるか聞かれたところ、できないくせにこだわり、思いだけは強かったので、「小麦粉は一切入れません」と答えました。今思うとなんて無謀だったと思いますが、経験がない分言うだけ言ってみようと言う気持ちでしたね。
研究センターには2週に1度のペースで、1年以上は通いました。ここで「えすぽわーる」をオープンしてからも関わりがありましたね。当時は、ソバ粉100%でこだま酵母を使ったお菓子を商品化したいと思っていました。
私が研究センターに通っているのと同時並行で、主人はソバの栽培と工房を建てる土地を探していました。私は工房を持つのはまだまだ先かなと思っていた矢先、中古のオーブンをはじめ工房に必要な設備が安く手に入るという情報が入りました。
即決しなくてはいけない状況で見せてもらい、私は自分が背中を押されているような気がして、購入を決めました。実は、昨年になって分かったのですが、藤里町にパンづくりを教えに東京から来ていただいている「サラ秋田白神」代表の津田雅俊さんが昔使っていたオーブンでした。不思議な縁ですね。
購入を決めた設備をそれから数か月内には移動させなくていけない状況だったので、急きょ今の場所の清水岱に工房を建てることに決めました。商品についても商売についても何も知らないのに、とにかく2009年11月7日のオープンに合わせて、見切り発車でのスタート。
始めてしばらくしても、研究センターに通って指導を受けながらお菓子を作っていました。昨年で丸10年。よく続きました。

不思議なつながりを感じるオーブン。
この歳でこんな経験ができると段々と楽しめるように
『えすぽわーる』は月曜定休なので、日曜の仕事が終わってから自宅のある秋田市に戻り、再び水曜朝に藤里に出かけてくる生活です。秋田市では週に1度、趣味でボウリングをやっています。クラブに入り、終わったら仲間とランチを楽しみます。あとは、買い出しや納品、取り引き先との打合せや営業にまわったりもしています。
お店オープンの時から、ソバ粉のロールケーキはありました。当時米粉のロールケーキはあったので、ソバ粉100%でできるのかなと思って試作をしたら、それほど苦労せずにできました。
でも、ソバ100%のパンを作るのは難しいです。こだま酵母を扱うのが難しいので。今ソバのパンを作っているけれど、そこには小麦粉を入れています。始めた当時は、ソバ100%でやろうとしたから大変でした。
あと焼き菓子、ボーロなども。それと、研究センターに通っていた時に作り方を相談していたパウンドケーキのようなお菓子も、お店ができた時に商品化しました。でも、常に安定して作るのは難しく、また、お菓子でもパンでもないものだったからお客さんに受け入れてもらうのが大変で、今は作っていません。
慣れないことだらけの状況でスタートしたので大変でした。このままでいいのかなという不安もありましたね。お客さんは、最初は興味を持って買ってくれるけれど、続けて買ってくれるのかと不安になったり、あとここの工房だけの販売でまだ販路がなかったり……。今となってはあまり覚えていないけれど、相当頭を悩ませていたように記憶しています。
そばの栽培と事務的なことは主人、お菓子の製造は私と役割分担をしていました。営業にも行きましたね。卸先へも営業、補助金のための申請書の作成、プレゼンの準備など初めてのことばかりで苦痛でした。でも次第にこの中で楽しめばいいんだなと思えるようになってきて、この歳でこんな経験ができるなんて考え方ひとつで状況が変わることを学びました。
商品を二ツ井の道の駅(能代市)、秋田自動車道の錦秋湖サービスエリア(岩手県西和賀町)のほか、関西のスーパーに不定期で卸したり、あとはネット販売も行っています。商談会で仲介してもらってAmazonにも。
県主催の秋田や東京で開催される商談会に参加したり、以前はFOODEX JAPAN(フーデックス、国際食品・飲料展)にも声がかかれば出展していました。でも、製造の限界もあるので、そこまで広げる必要もないのかなあと段々と分かってきました。
以前商談会に参加していた時は、必死に取引をお願いしますという姿勢で行っていたけれど、今はいろんな横のつながりができればいいなあと余裕を持って参加できるようなりました。10年経って、そう思えるようになりましたね。

(後編へ続く)
*旅する藤里「菓子工房 えすぽわーる」 後編
https://www.town.fujisato.akita.jp/kanko/notices/2079
*旅する藤里 まとめページへ
https://www.town.fujisato.akita.jp/kanko/notices/2496
ライター : 久保田真理(くぼた・まり)
ライフスタイル誌の編集者、オーストラリアでの写真留学を経て、フリーランスとして独立。国内外の取材を通じて、多様な生活や文化の魅力を発信する。秋田市生まれ、茨城・千葉育ち。趣味は、日本酒、トレイルランニング、ソウルミュージックの世界に浸ること。
知られざる藤里の旅は、“大切なものは何か”気付かせてくれるはずです。
このコラムは聞き書きの手法で藤里町ツーリズム協議会が制作しお届けしています。
藤里町ツーリズム協議会 電話0185-79-2115
*白神山地ふじさとのストーリーが届くフェイスブックはこちらです*
フォローすると定期的にストーリーが届きます
https://www.facebook.com/fujisato.syoukoukankou/